Torpedoes, Mine
Torpedoes, Mine
| アイコン | 意味 |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |

- ※“プロジェクトG-6 Project G-6”として知られる特殊な航空魚雷の開発は、1925年2月に開始された。この開発は1926年に中止され、代わりにMk. 7の航空版にさらなる改良が加えられた。しかし、この改良は成功せず、G-6計画は1927年に復活。これは1930年8月に正式にMk. 13と命名されたが、米海軍が雷撃機の将来に疑問を呈したため、10月に開発はふたたび中止。急降下爆撃機が好まれるようになったため、新型の航空母艦レンジャー Ranger(CV-4)は魚雷の格納庫を全く備えずに設計された。雷撃機への関心も完全に失われたわけではなく、将来の飛行機用に新しい、より軽量な1,000ポンド(454kg)の魚雷が検討された。この設計は非実用的であることが判明したため、Mk. 13開発プロジェクトは1931年7月にふたたび復活した。Mk. 13魚雷の最初の成功した発射は1932年3月に行われ、2番目の試作機は6,000ヤード(5,500m)以上の飛行中に30ktの速度を記録した。1935年には空中テストが続き、5月27日から10月1日の間に少なくとも23回の投下が行われ、1936年にはさらに20回が行われた。最終的に、1938年にMk. 13はアメリカ海軍で採用された最初の特別に設計された航空機魚雷となった。これは第二次大戦中、アメリカで最も多く使用された航空魚雷となった。ほかの海軍の航空魚雷とは大きく異なり、短くて太いのに対し、短くて細いのが特徴。また、比較的低速で射程が長いのも特徴
- ※1930年代に開発されたほかの米海軍の魚雷とは異なり、太平洋戦争開戦当初、Mk. 13は磁気爆発装置を搭載していませんでした。当初のTNT爆薬はMk. 4 Mod. 1接触型爆発装置を使用し、のちのトルペックス爆薬はMk. 8接触型爆発装置を使用していた。Mk. 9と命名された磁気爆発装置は、1945年3月頃に導入された。この爆発装置は、潜水艦用のMk. 16(過酸化水素)魚雷とMk. 18(電気式)魚雷にも配備された(下記参照)。これは戦争終盤の出来事であるため、この爆発装置を搭載したMk. 13魚雷が実戦で使用されたかどうかは定かではない。例えば、1945年4月の戦艦大和攻撃に使用された起爆装置は、全て接触型だったようだ
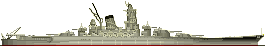
- ↑大和型戦艦大和(1945年時)
- ※1930年代後半までに、Mk. 13 Mod. 0魚雷は156本が製造。これは、戦前の空母艦隊に配備されていた18機の雷撃飛行隊4個にそれぞれ2発の弾薬を供給できる量で、さらに予備機12発分を供給できた。Mod. 0は、後継のMod. とは異なり、プロペラが舵の前方に位置するレール式の尾部を備えていた。この特徴を持つアメリカの魚雷はMod. 0のみ。ニューポート魚雷基地 Newport Torpedo Stationは理由は不明ですが、この配置に不満を抱き、1940年にMod. 1が従来のプロペラ配置で就役。残念ながら、Mod. 0とは異なり、Mod. 1は信頼性の低い兵器であることが判明。1941年7月の演習でVT-6が投下した10発の魚雷のうち、高温で直線的に正常に航走したのはわずか1発。残りの4発は沈没して回収できず、残りの5発は不安定な航走をした。これらの問題は戦争初期まで続き、1943年半ばに150ktを超える速度で投下された105発の魚雷を分析したところ、36%が低温航走(始動せず)、20%が沈没、20%が偏向性能不良、18%が深度性能不良、2%が水面到達、そして良好な航走はわずか31%だった。複数の欠陥を持つ魚雷が多かったため、合計は100%を超えている。初期型は、魚雷を低高度(通常は高度50フィート(15m)、速度110kt)でゆっくりと投下する必要があったため、さらに不利な状況にあった。そのため、魚雷を搭載した機体は攻撃に対して脆弱だった
- ※これらの問題は、戦争後期には大幅に軽減された。魚雷にはフィン・スタビライザー、ノーズ・ドラッグ・リング、テイル・シュラウド・リングが追加され、投下後に魚雷の速度を減速させ、機首から着水し、許容できる速度で着水するようにした。これにより投下特性が改善され、航空機の推奨最大発射高度は2,400フィート(730m)、速度410ktにまで引き上げられた
- ※魚雷の尾部にはランヤードが取り付けられていた。投下されるとランヤードが始動レヴァーを作動させるが、着水遅延弁が作動し、魚雷が着水するまで燃焼フラスコへの点火は停止しない。150kt以上の速度で投下された場合、魚雷は26゚から30゚の角度で着水。水深は少なくとも150フィート(45m)必要であり、魚雷は300ヤード(275m)着水すると設定された航走深度に達する。起爆装置は200ヤード(180m)着水すると作動する。深度は最大50フィート(15m)まで設定可能
- ※先端ドラッグ・リングの追加により、飛行中の魚雷の安定性が向上し、対気速度が約40%低下し、空力性能が向上。また、魚雷が着水した際のショック・アブソーバーとしても機能した。尾部シュラウド・リングは、フックとブローチを減らし、初期のMk. 13の特徴であった水中ロールを大幅に排除することで、水中走行を改善。高温で直線的で正常な走行が100%に近づいた。大幅に改良された魚雷の入手性を高めるため、兵器局はシュラウド・リングを取り付けた尾部アセンブリを製造し、これを既存の在庫品のアップグレード用に艦隊に出荷。1944年の秋までには、改良された魚雷は前線の空母部隊で一般的に使用され、彼らは熱烈な賞賛を表明した。1945年の初めのあるとき、6本の魚雷が高度5,000~7,000フィート(1,500 ~2,100m)から投下されました。6本のうち5本が高温で直線的で正常な走行を示したことが観測された。終戦までに、米海軍はMk. 13をどの国が製造した航空魚雷の中でも最高のものとみなし、1951年まで運用を続けた
- ※PTボートは当初、大型の水上艦用魚雷発射管から発射するMk. 8魚雷4本を搭載していた。1943年半ばには、これらの魚雷は、簡素な発射機構から発射するMk. 13魚雷への更新が始まった。これにより大幅に軽量化された重量を、PTボートの砲兵装に充てることができた
- ※Mk. 13は、米海軍が実戦で使用した最後の魚雷であり、世界でも最後に実戦で使用された航空魚雷としても知られている(2010年12月現在)。1951年5月1日、通常攻撃による爆撃が失敗に終わった後、海軍は北緯38度線のすぐ北、北漢江に位置する華川ダムの水門に魚雷を投下することを決定しました。北朝鮮軍はダムの水門を自軍の兵力移動の支援と連合軍の兵力移動の妨害に利用していた。航空母艦プリンストンPrinceton(CV-37)はAD-4スカイレイダー5機とAD-4Nスカイレイダー3機を派遣し、各機からダムに向けてMk. 13魚雷1発を発射。1発は不発、もう1発は誤射しましたが、残りの6発は水門を開放し、北朝鮮による河川水系の支配を終わらせることに成功

↑A Douglas AD-4 Skyraider from Attack Squadron (VA) 195 "Tigers" carrying a Mk. 13 torpedo en route to the Hwacheon Dam in Korea, 1 May 1951. The nose of the torpedo is surrounded by a plywood "drag ring" that slowed its flight and entry into the water, and a protective plywood box around the tailfins and propeller that would likewise break off on impact. VA-195 was assigned to Carrier Air Group (CVG) 19 aboard USS Princeton (CV-37) for a deployment to Korea from 9 November 1950 to 29 May 1951. The squadron was renamed "Dambusters" following this successful attack. U.S. Navy photo. Image courtesy of NavSource.
- ※第二次大戦中、Mk. 13魚雷は合計17,000発が製造された
| ヴァリエーション | |
| Mod. 1 | 尾翼の改良、プロペラの強化、舵をプロペラの前方に移動 |
| Mod. 2 | 40ktの試験用魚雷(開発中止) |
| Mod. 3 | 外部ジャイロ設定を追加 |
| Mod. 4 | 試験モデル。強化後胴体付きで50発生産 |
| Mod. 5 | Mod. 1にウォーター・トリップを追加 |
| Mod. 6 | Mod. 2Aにシュラウド・リングを追加 |
| Mod. 7 | Mod. 3にシュラウド・リングを追加 |
| Mod. 8 | Mod. 4にシュラウド・リングを追加 |
| Mod. 9 | Mod. 5にシュラウド・リングを追加 |
| Mod. 10 | 胴体、シュラウド・リング、サスペンション・ビーム、ジャイロ・アングルを削除後に強化 |
| Mod. 11 | Mod. 6をサスペンション・ビームに対応するように改造 |
| Mod. 12 | Mod. 7をサスペンション・ビームに対応するように改造 |
| Mod. 13 | Mod. 9をサスペンション・ビームに対応するように改造 |
※第二次大戦中の成功率ノーマン・フリードマン Norman Friedman著「US Naval Weapons」より:“戦争経験の検討によると、合計1,287回の攻撃があった[この数には空母搭載機による攻撃のみが含まれており、その他の米海軍機による攻撃は150回行われた]魚雷(TD)のうち40%(514発)が命中し、そのうち50%は戦艦と空母(ミッドウェーを含む322回の攻撃)、31%は駆逐艦(179回の攻撃)、41%(445回の攻撃中)は商船に命中した”フリードマン博士は言及していないが、戦時中、少なくとも8隻の日本巡洋艦が航空魚雷の被弾を受けている
| スペック | |
| 全長 | |
| 重量 | |
| 負浮力 | 237.22kg |
| 航続距離/速力 | |
| 炸薬 | |
| 誘導 | Mk. 12 Mod. 1 ジャイロ |
| 動力源 | 湿式加熱式蒸気タービン |
| 備考 | |
Update 25/06/22